コレクション: 琉球の風を感じるやちむんのうつわ

画像は「【渡慶次工房】6寸皿 [3]」
やちむんは、ひと目でそれとわかる。沖縄の海の色、大地の色、森の色が大胆に描かれ、登り窯で重ねて焼くためにできる輪っか「蛇の目」も特徴的だ。陶土はもちろん、釉薬もほとんど沖縄の自然物からつくったものだと 「北窯」の松田米司さん。
やちむんの歴史は王国時代にさかのぼる。朝鮮人陶工から伝えられた焼物づくりは沖縄の風土に合い、1682年、王府が製陶産業の振興のために那覇の壺屋に窯を統合した。中国や薩摩、南方からの技術も合わさって独自に発展。柳宗悦らの民藝運動も後押しし、やちむんは全国に知られるようになる。

画像は「【神谷窯】7寸皿 [13] - A」
1970年代、壺屋で登り窯の使用が禁止されると、読谷村に新しい窯をという流れが起きた。当時、米司さんは、師である大嶺實清さんの首里にある石嶺窯まで、自宅があった読谷から通っていた。
「読谷は米軍の不発弾処理場でしたが、琉球文化を誇りに思う人たちが、ここに文化村をつくろうとしていた。爆弾の煙ではなく、焼物の煙を上げようと」。
1972年、のちに人間国宝となる金城次郎さんが壺屋から読谷へ。1980年には大嶺さんら陶工4名も読谷に移って共同登り窯を築き、やちむんの里が形成されていく。
- text: Yukie Masumoto Discover Japan 2024年7月号より引用
-
![【育陶園】唐草手碗(白)[2]](//shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/ikutoen_2_20250306discover18880_sq.jpg?v=1743665688&width=533) 売り切れ
売り切れ【育陶園】唐草手碗(白)[2]
通常価格 ¥5,500通常価格単価 / あたり -
【育陶園】唐草手碗(飴)[5]
通常価格 ¥5,500通常価格単価 / あたり -
![【育陶園】唐草手碗(藍)[4]](//shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/ikutoen_4_20250306discover18885_sq.jpg?v=1743665775&width=533) 売り切れ
売り切れ【育陶園】唐草手碗(藍)[4]
通常価格 ¥5,500通常価格単価 / あたり -
![【育陶園】唐草手碗(緑)[3]](//shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/ikutoen_3_20250306discover18882_sq.jpg?v=1743665735&width=533) 売り切れ
売り切れ【育陶園】唐草手碗(緑)[3]
通常価格 ¥5,500通常価格単価 / あたり -
![【育陶園】唐草手碗(墨)[1]](//shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/ikutoen_1_20250306discover18877_sq.jpg?v=1743664830&width=533) 売り切れ
売り切れ【育陶園】唐草手碗(墨)[1]
通常価格 ¥5,500通常価格単価 / あたり -
【工房クバヤー】7寸皿 [24]
通常価格 ¥6,600通常価格単価 / あたり -
【北窯 宮城工房】8寸皿 [20]
通常価格 ¥8,580通常価格単価 / あたり -
【神谷窯】8寸皿 [14]
通常価格 ¥8,580通常価格単価 / あたり -
【神谷窯】7寸皿 [13]
通常価格 ¥6,270通常価格単価 / あたり -
![【いずみ窯 島袋工房】6寸皿 [8]](//shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/yachimun_izumi_shimabukuro_08_119-2172.jpg?v=1741678590&width=533) 売り切れ
売り切れ【いずみ窯 島袋工房】6寸皿 [8]
通常価格 ¥3,960通常価格単価 / あたり -
【渡慶次工房】5寸皿 [4]
通常価格 ¥3,080通常価格単価 / あたり -
【渡慶次工房】6寸皿 [3]
通常価格 ¥4,400通常価格単価 / あたり -
【渡慶次工房】7寸皿 [2]
通常価格 ¥6,600通常価格単価 / あたり
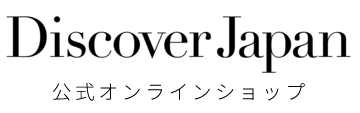
![【育陶園】唐草手碗(白)[2]](http://shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/ikutoen_2_20250306discover18880_sq.jpg?v=1743665688&width=533)
![【育陶園】唐草手碗(飴)[5]](http://shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/ikutoen_5_20250306discover18868_sq.jpg?v=1743665769&width=533)
![【育陶園】唐草手碗(藍)[4]](http://shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/ikutoen_4_20250306discover18885_sq.jpg?v=1743665775&width=533)
![【育陶園】唐草手碗(緑)[3]](http://shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/ikutoen_3_20250306discover18882_sq.jpg?v=1743665735&width=533)
![【育陶園】唐草手碗(墨)[1]](http://shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/ikutoen_1_20250306discover18877_sq.jpg?v=1743664830&width=533)
![【工房クバヤー】7寸皿 [24]](http://shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/yachimun_kubaya_24_1_119-2225.jpg?v=1741678697&width=533)
![【北窯 宮城工房】8寸皿 [20]](http://shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/yachimun_kitagama_miyagi_20_119-2185.jpg?v=1741679125&width=533)
![【神谷窯】8寸皿 [14]](http://shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/yachimun_kamiya_14_119-2161.jpg?v=1741678647&width=533)
![【神谷窯】7寸皿 [13]](http://shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/yachimun_kamiya_13_KV_119-2192.jpg?v=1744689092&width=533)
![【いずみ窯 島袋工房】6寸皿 [8]](http://shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/yachimun_izumi_shimabukuro_08_119-2172.jpg?v=1741678590&width=533)
![【渡慶次工房】5寸皿 [4]](http://shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/yachimun_tokeshi_04_1_119-2243.jpg?v=1741678336&width=533)
![【渡慶次工房】6寸皿 [3]](http://shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/yachimun_tokeshi_03_KV_119-2252.jpg?v=1744689165&width=533)
![【渡慶次工房】7寸皿 [2]](http://shop.discoverjapan-web.com/cdn/shop/files/yachimun_tokeshi_02_1_119-2290.jpg?v=1741677928&width=533)