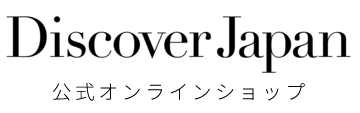圡楽窯の土鍋について。ご購入・ご使用の前に、必ずご一読ください
伊賀土でつくられた圡楽窯の土鍋は使い込んで育てていく「料理の道具」。育つにつれて焼き加減や煮込み具合が唯一無二のものになっていきます。「お肉を"この鍋で"焼くと」「料理を”この鍋で"煮込むと」……というように、鍋そのものがレシピの一部になるような、頼もしい日本古来の道具です。
この土鍋は使い続けるにあたって「ヒビ」が必ず入ります。ヒビも含めて育てていただくことで長くご愛用いただける道具となっておりますため、ご理解いただけますと幸いです。
ヒビと貫入について

伊賀の土を使った圡楽窯の土鍋は、性質上必ずひびが入ります。釉薬がかかっている部分に入るヒビは貫入といって、素地と釉薬の収縮率の違いによりできるものです。貫入とひびが土鍋の膨張を分散させ、ぱっくり割れるのを防いでくれるため、とても大事なものです。
土鍋は火にかけた段階で膨張と収縮を繰り返し、土鍋の内側・鍋底の裏にひびが入ります。伊賀の土鍋に必ず起こる現象で、 このヒビが入ってからどんどん煮えやすくなり、 鍋が成長していきます。
実はこの貫入とヒビが、土鍋の膨張を分散させ、ぱっくり割れるのを防いでいるのです。
3年ほど使った白い土鍋の例

表面に地割れのようなヒビが入っています。これを貫入(かんにゅう)と呼び、土鍋以外の陶器作品などでも長く使うと見える現象です。陶器作品では、釉薬の表現や経年変化で起きるものとして、うつわの世界では景色として愛でる文化もございます。
土鍋は火にかけるため、陶器作品よりも早く貫入の変化が起きます。火にかけるため、底面にも必ずヒビがはいります。

焦げは落とさず、なるべくそのままにして、使うものとなります。底面には釉薬がかかっていないので、ゴシゴシと無理にこすって洗うのは寿命が短くなる原因となります。

土鍋の鍋底の裏に入ったひびの事例です。火にかけていて、ひびからぽたぽたと水が漏るようになったら、おかゆを炊いてください。問題なくご使用いただけます。
釉薬の剥離について

鍋の中の釉薬が剥離することもあります。うつわと違い、火にかける道具なのでこういったことも起きます。
<釉薬が剥離した場合の対応方法>
- 別のお鍋でお粥を炊いてください。
- 剥がれた個所を重点的にやわらかめのご飯粒をヒビに沿って擦り込み
- 別のお鍋で炊いたお粥を土鍋に移し焦がさないようにお水を足しながらコトコトと1時間くらい炊いてください。1日おいて洗い、よく乾かしてからご利用をお願いいたします。
よくないヒビの例

縁までひびが達している場合は、使用中に割れてしまう危険がございますのでご使用にならないでください。
- 火力が強すぎた
- 物をおとした
- 何か当たってしまった
など、物理的な衝撃が加わってしまったことが原因です。
土鍋は陶器なので、落としたりぶつければ割れてしまいます。割れ物としてお取り扱いください。
※土鍋の性質上、金継ぎを含め、修復は不可となります。
圡楽窯の鍋は他の土鍋より何故ヒビが入るのか?
昔ながらの土鍋は本来貫入とヒビが入るもの。圡楽窯は古くから伝わる日本の土鍋の作りをしており、伊賀に伝わる土鍋の伝統を守って作られています。
日本製の土鍋であっても、簡易に使える外国の土を使用し「ペタライト」が含まれる近年主流の土鍋とは構造が全く違う、より伝統的な土鍋です。
土鍋を育てる上で重要なこと
-
最初の目止め
使い初めにお粥を炊き目止めを行います。(詳細は同梱の説明書を確認ください)理由の一つとしては、水漏れを抑えること。二つ目の理由はよいひびや貫入を入れることです。
目止めが完全にできていない場合は水漏れを起こすこともございますので、最初にお粥に浸ける時間を48時間をしっかりと守る(もしくは何回か繰り返す)ことで水漏れが止まります。
-
火加減
土鍋は土でできています。火にかける準備を鍋にしてもらう必要があります。いきなり強火にかけると、土が温まっていないことから大きな悪いヒビが入るリスクが高まります。
弱火(鍋が育ってきたら弱めの中火が可能に)→中火→強火の順であたためていただく必要があります。
一度全体があたたまると圡楽鍋の本領発揮!保温が長く、お肉やご飯はやわらかく火が通り、美味しく煮込むことができます。火加減に関しては『小さな五徳』を置くことにより火のあたりも優しくなり土鍋の持ちもよくなります。
圡楽窯の商品一覧はこちらから |